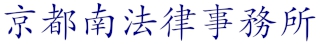弁護士の “やましろ”探訪 〜古から現代へ〜
栗隈大溝(くりくまのおおうなで)
杉山 潔志
 ▲ 今池川北側の小樋尻遺跡発掘場所
▲ 今池川北側の小樋尻遺跡発掘場所
〔小樋尻遺跡の発掘調査〕
2017年度から実施された新名神高速道路整備事業・国道24号寺田拡張事業に伴う小樋尻(こひじり)遺跡(京都府城陽市富野久保田)の第10・11次調査(2022年4月〜2021年2月)で、鍬、鋤などの木製農具とともに古墳時代前期前葉の自然流路と古墳時代後期後葉に掘られ奈良時代まで使用された人工的な溝が発見されました。自然流路と溝は重複しており、改修をしながら使用されていたと考えられています。
自然流路は縄文・弥生時代の流路に一部手を加えた幅約25m、深さ約2.7mの流路で、木材を杭で固定して水流を調節する施設や祭祀に用いられたと思われる導水施設が発見されました。人工的な溝は、幅約11m、深さ約1.8mで、造成された溝底の両側の下層に草本類を敷き造成土を強化する高度な土木技術(敷葉工法)が用いられ、溝の北側に水位を調整する木製の堰が設けられていました(京都府埋蔵文化財調査研究センターのホームページ)。
小樋尻遺跡は、古川の支流今池川の近くにあり、発掘された流路や溝が日本書記に記された栗隈大溝ではないかと指摘されています。
2017年度から実施された新名神高速道路整備事業・国道24号寺田拡張事業に伴う小樋尻(こひじり)遺跡(京都府城陽市富野久保田)の第10・11次調査(2022年4月〜2021年2月)で、鍬、鋤などの木製農具とともに古墳時代前期前葉の自然流路と古墳時代後期後葉に掘られ奈良時代まで使用された人工的な溝が発見されました。自然流路と溝は重複しており、改修をしながら使用されていたと考えられています。
自然流路は縄文・弥生時代の流路に一部手を加えた幅約25m、深さ約2.7mの流路で、木材を杭で固定して水流を調節する施設や祭祀に用いられたと思われる導水施設が発見されました。人工的な溝は、幅約11m、深さ約1.8mで、造成された溝底の両側の下層に草本類を敷き造成土を強化する高度な土木技術(敷葉工法)が用いられ、溝の北側に水位を調整する木製の堰が設けられていました(京都府埋蔵文化財調査研究センターのホームページ)。
小樋尻遺跡は、古川の支流今池川の近くにあり、発掘された流路や溝が日本書記に記された栗隈大溝ではないかと指摘されています。
 ▲ 寺田大野で西から北へ流れる今池川
▲ 寺田大野で西から北へ流れる今池川
〔日本書記に記された栗隈大溝〕
日本書記の仁徳天皇十二年十月条には「大溝を山背の栗隈県に掘りて田に潤く。是を以て、その百姓、毎に年豊」との記述があり、推古天皇十五年是歳条には「山背国に大溝を栗隈に掘る」との記述があります。栗隈は古代の山城国久世郡に置かれた十二郷の一つで、現在の京都府宇治市の大久保・広野とこれに隣接する城陽市の一部付近と推定されています。栗隈大溝については、その所在地や仁徳天皇12年(324年)の大溝と推古天皇15年(607年)の大溝が同一のものか否かが議論されてきました。
これまで、城陽市富野付近で木津川本川からの取水を想定した現在の古川を栗隈大溝に比定する考え方が有力に主張されてきました。城陽市を流れる古川や支流の今池川の流路は、東西から南北、南北から東西へと直角的に曲がっており、条理地割に沿って開削されたと想起させられます。
 ▲ 古川(左)・今池川(右)合流部
これに対し、古川説では大溝の灌漑地域が木津川右岸の西部低湿地帯に限られることや取水技術などを根拠に、城陽市から宇治市大久保の扇状地下を北流する大洲池水路(近鉄京都線の西側を北流)や久津川車塚古墳の南を西流して木津川に注いでいた大谷川を久津川車塚古墳の東で北北西に流路変更して大洲池水路に合流させた掘削部分を大溝とする考え方もあります(佐野静代「古墳時代における政治領域の空間構造」人文地理第47巻2号(1995))。低地を西流していた大谷川の流路の底部から高い北北西への変更は人為を感じさせます。また、大谷川北北西部流域の栗隈郷から名木郷に至る部分を仁徳朝の大溝、現在の古川を推古朝の大溝に比定する考え方も主張されています。
▲ 古川(左)・今池川(右)合流部
これに対し、古川説では大溝の灌漑地域が木津川右岸の西部低湿地帯に限られることや取水技術などを根拠に、城陽市から宇治市大久保の扇状地下を北流する大洲池水路(近鉄京都線の西側を北流)や久津川車塚古墳の南を西流して木津川に注いでいた大谷川を久津川車塚古墳の東で北北西に流路変更して大洲池水路に合流させた掘削部分を大溝とする考え方もあります(佐野静代「古墳時代における政治領域の空間構造」人文地理第47巻2号(1995))。低地を西流していた大谷川の流路の底部から高い北北西への変更は人為を感じさせます。また、大谷川北北西部流域の栗隈郷から名木郷に至る部分を仁徳朝の大溝、現在の古川を推古朝の大溝に比定する考え方も主張されています。
日本書記の仁徳天皇十二年十月条には「大溝を山背の栗隈県に掘りて田に潤く。是を以て、その百姓、毎に年豊」との記述があり、推古天皇十五年是歳条には「山背国に大溝を栗隈に掘る」との記述があります。栗隈は古代の山城国久世郡に置かれた十二郷の一つで、現在の京都府宇治市の大久保・広野とこれに隣接する城陽市の一部付近と推定されています。栗隈大溝については、その所在地や仁徳天皇12年(324年)の大溝と推古天皇15年(607年)の大溝が同一のものか否かが議論されてきました。
これまで、城陽市富野付近で木津川本川からの取水を想定した現在の古川を栗隈大溝に比定する考え方が有力に主張されてきました。城陽市を流れる古川や支流の今池川の流路は、東西から南北、南北から東西へと直角的に曲がっており、条理地割に沿って開削されたと想起させられます。
 ▲ 古川(左)・今池川(右)合流部
▲ 古川(左)・今池川(右)合流部
 ▲ 荒州南橋上流で西から北へ流れる古川
▲ 荒州南橋上流で西から北へ流れる古川
〔現在河川・用水路と水利権〕
古川、今池川の周辺地域には現在も農地が広がり、農業用水路が網の目のように存在しています。この地域の農業用水は、これまで木津川からの取水や東部丘陵を源とする小河川・湧水が利用されていたようですが、現在では、揚水ポンプで汲み上げられた地下水が農地に供給されるようになり、古川や今池川は排水路化しているようです。
古川や今池川から灌漑していた時代には、その流水に水利権が成立していたと考えられます。水利権は、水力発電、灌漑、水道などの利用に必要な流水を排他的・継続的に使用する権利です。権利の永続性、第三者に対する効力や優先的効力が認められることなどに照らし、契約によって成立する債権ではなく、物権ないし物権的権利(慣行水利権)とされ、専用権、共用権、余水利用権に分類されています。民法第175条は「物権は民法その他の法律に定めるもののほか創設できない」と定めており(物権法定主義)、慣行水利権は、その例外とされています。水利権は水利使用の目的がなくなった場合や水源が枯渇すると権利も消滅するという特殊性を有しています。
古川、今池川の周辺地域には現在も農地が広がり、農業用水路が網の目のように存在しています。この地域の農業用水は、これまで木津川からの取水や東部丘陵を源とする小河川・湧水が利用されていたようですが、現在では、揚水ポンプで汲み上げられた地下水が農地に供給されるようになり、古川や今池川は排水路化しているようです。
古川や今池川から灌漑していた時代には、その流水に水利権が成立していたと考えられます。水利権は、水力発電、灌漑、水道などの利用に必要な流水を排他的・継続的に使用する権利です。権利の永続性、第三者に対する効力や優先的効力が認められることなどに照らし、契約によって成立する債権ではなく、物権ないし物権的権利(慣行水利権)とされ、専用権、共用権、余水利用権に分類されています。民法第175条は「物権は民法その他の法律に定めるもののほか創設できない」と定めており(物権法定主義)、慣行水利権は、その例外とされています。水利権は水利使用の目的がなくなった場合や水源が枯渇すると権利も消滅するという特殊性を有しています。
 ▲ 荒州北橋を北流する古川
▲ 荒州北橋を北流する古川
〔河川からの取水と慣行水利権〕
河川法第23条は、河川の流水を占用しようとする者は河川管理者の許可を受けなければならないと定めています。この規定によって許可された流水占用権を許可水利権といいます。他方、河川法第87条は、河川や河川区域などの指定の際に権限に基づいて河川工作物を設置しているものは河川法による許可・登録を受けたとみなすと定めており、河川法施行法により旧河川法(明治29年4月8日法律第71号)、河川法施行規程(明治29年勅令第236号)で是認された慣行水利権は、取水施設の安全性や河川流量との関係が審査されていないことや取水報告がなく取水量が明確になっていないことなどの問題点が指摘されており、施設の改築等の機会を捉えて許可化が促されています(国土交通省のホームページ)。
河川法第23条は、河川の流水を占用しようとする者は河川管理者の許可を受けなければならないと定めています。この規定によって許可された流水占用権を許可水利権といいます。他方、河川法第87条は、河川や河川区域などの指定の際に権限に基づいて河川工作物を設置しているものは河川法による許可・登録を受けたとみなすと定めており、河川法施行法により旧河川法(明治29年4月8日法律第71号)、河川法施行規程(明治29年勅令第236号)で是認された慣行水利権は、取水施設の安全性や河川流量との関係が審査されていないことや取水報告がなく取水量が明確になっていないことなどの問題点が指摘されており、施設の改築等の機会を捉えて許可化が促されています(国土交通省のホームページ)。
※写真をクリックすると大き表示します。
-
 ▲ 久世上大谷付近を西流する大谷川
▲ 久世上大谷付近を西流する大谷川
-
 ▲ 下大谷バス停付近で北西へ流れる大谷川
▲ 下大谷バス停付近で北西へ流れる大谷川
2025年9月